太陽光発電は固定買い取り制度が、
ドイツから数年遅れて、
かなりの高価格でスタートしたため、
早い者勝ちのゲームになり、
すぐに制度矛盾が露呈し、
買取価格は毎年大幅に下げられた。
固定買い取りの期間は、
一般家庭は10年、
産業用は20年とされた。
20年というのは
定期借地権の期間と同じで、
土地を借りる方にも都合が良かった。
買取制度も終了しつつあり、
新規のソーラーは採算性が低くなっている。
すでに、投資の対象にはならない。
買取義務の終了した太陽光発電はどうなるのか?
国も制度終了後の方向性を模索している。
自治体向けに
・買取期間終了後の再エネ活用 事業の実現可能性調査支援
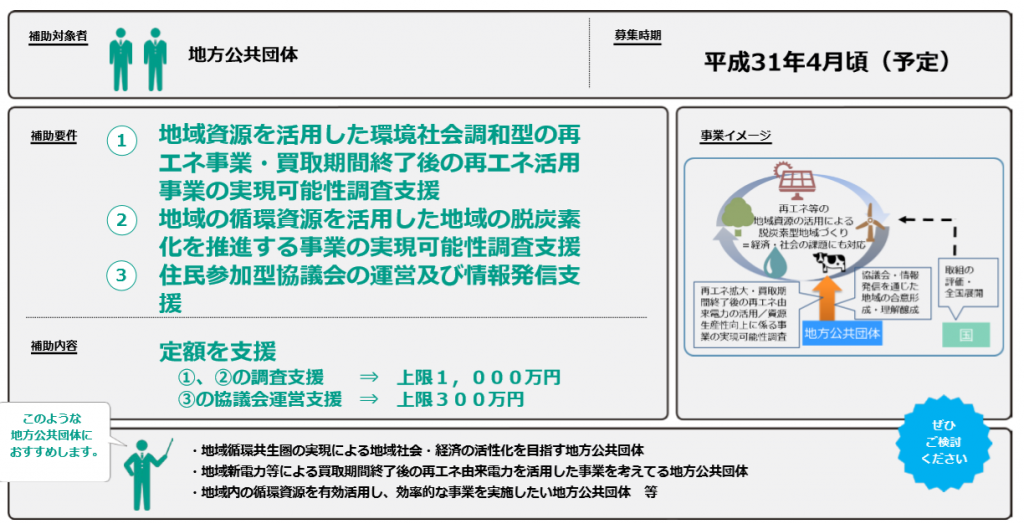
という補助金を出している。
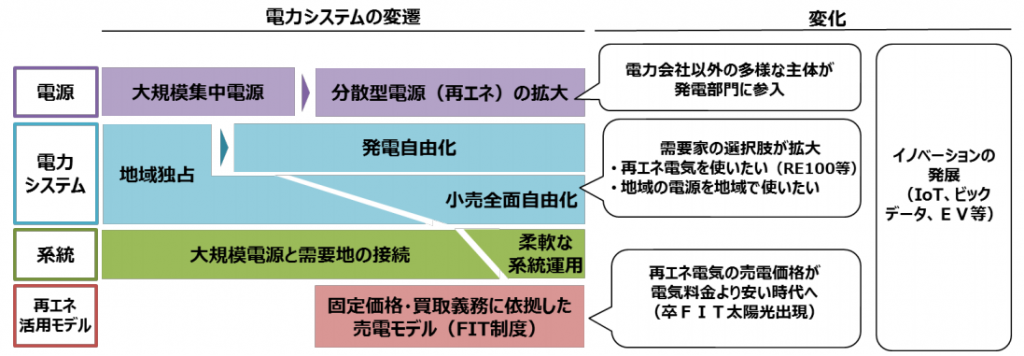
すでに買取義務の終了した太陽光発電は、
電力会社が次の買取条件を提示している。
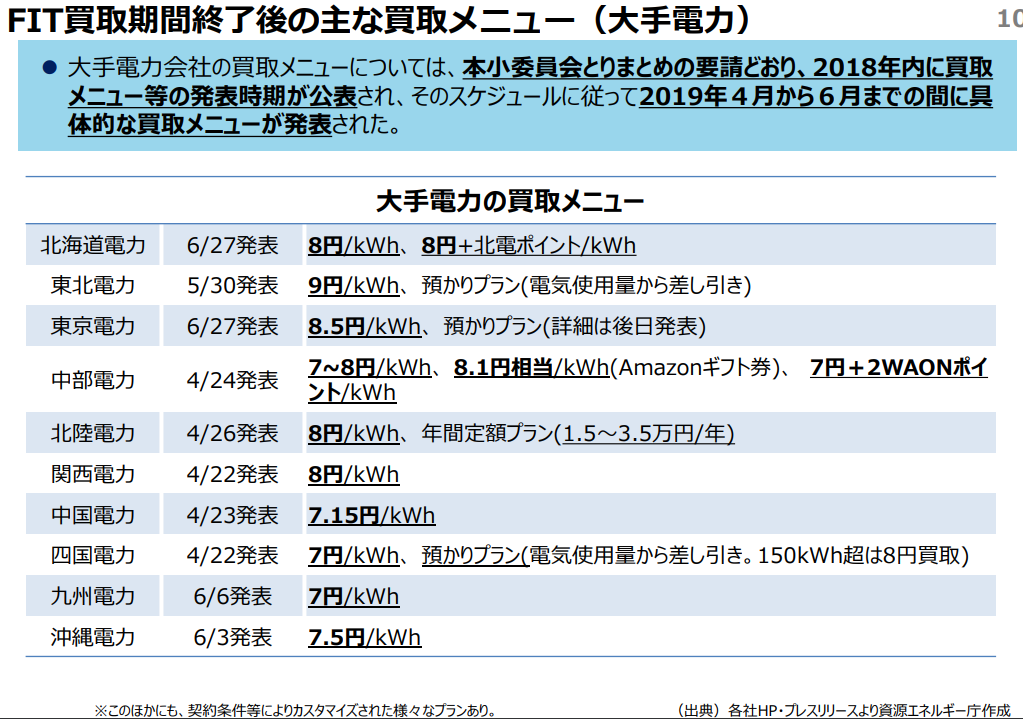
これを見ると、
買取の条件を
自社から電気を買うこと
としてる場合もあり、
新たな囲い込み制度のようにも感じる。
自由化の名のもとに、仕組みが多様化するのはいかがなものか?
我々は
エネルギー最適化コンサルタントとして、
顧客にアドバイスする立場だ。
これだけ複雑なゲームになれば、
中小企業の経営者が自ら選択することは難しいと思える。
参考資料
更なる再エネ拡大を実現するための エネルギー需給革新の推進 ~需給一体型モデルの活用~
2019年7月5日 資源エネルギー庁